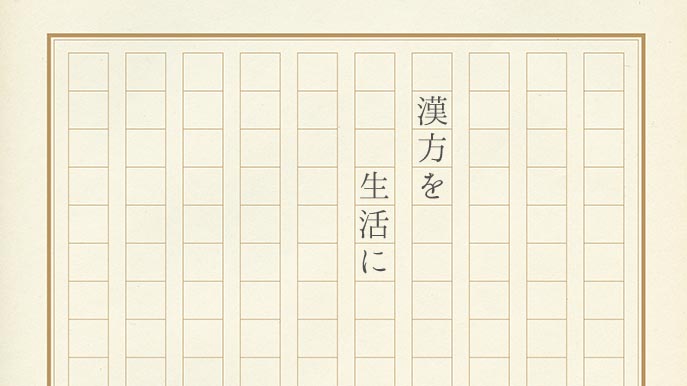【漢方薬のはなし】風邪には葛根湯だけしかない??
中国ではあまり葛根湯は使われない?
日本では、風邪の漢方薬というとすぐに葛根湯が頭に浮かぶかと思います。“すぐに”と書きましたが、“すぐに”というか、葛根湯、それしか思い浮かばないのではないでしょうか?
しかしこの葛根湯、漢方薬の本場である中国ではほとんど使われていません。
葛根湯は、今から2000年近く前に著された『傷寒論』に収載されている漢方薬です。この『傷寒論』は、「医聖」と呼ばれる張仲景の手によってまとめられた、漢方薬の原典です。つまり、葛根湯は、漢方薬の中でも最も古いものの一つで、由緒ある処方ということが言えます。
では、なぜ中国で葛根湯は使われなくなってしまったのでしょうか?
『傷寒論』の時代背景
『傷寒論』が書かれた時代は、今よりも気候が寒かったと言われています。さらに加えて、栄養状態が悪く、また、当時はまだ人類にとって未知のウイルスや細菌が多く、それに対する抗体を人間が持っていなかったという背景があります。
そのため、この時代は寒さによる風邪が多く、寒さへいかに対応するかが風邪治療の主流でありました。『傷寒論』の書名からも分かるように、“傷寒”とは、寒さによって危害を受けた病という意味であり、その病への対処法(漢方処方)をまとめたものが『傷寒論』ということなのです。
以上のことから分かるように、『傷寒論』に収載されている漢方薬は、寒さに対抗するために編み出されたものなので、身体を温めることが主眼になっていました。
葛根湯もこの『傷寒論』の“寒さ”へ対応する時代の処方ですので、寒さに対して温めることを主眼にしているわけです。
明・清の時代へ
この『傷寒論』の時代を経て数百年経ち、明や清の時代になると、都市の規模が格段に大きくなって人口が密集するようになり、上下水道などの汚染が増えてきました。そしてそれらの都市には様々な地方から人が行き交うため、ウイルスの変異が進んだり、人口増大に伴って未知の土地を切り開くなどしたために、未知のウイルスに触れる機会も増えていきました。また、さらに太陽黒点の変動といった自然環境の変化による地球の温暖化もあり、かつての寒さによる風邪への対処だけでは追いつかなくなってきたわけです。
つまり『傷寒論』は寒さに抵抗する処方集だったので、それでは間に合わなかったため、今度は「温熱」によって生じる風邪に対応する処方の登場が必要になっていたわけです。
そこで、このような時代に現れた新しい処方体系が「温病学」と呼ばれるものです。
その時代の必要性に応えるように、、『傷寒論』の時代には使われていなかった金銀花(キンギンカ)、連翹(レンギョウ)といった生薬も見出されるようになりました。
このような背景から生まれた漢方薬が、銀翹散(ぎんぎょうさん)といった処方になります。
青い風邪、赤い風邪
女優の綾瀬はるかさんが出演しているベンザブロックという西洋薬のCM(コマーシャル)で、「青い風邪には〇〇、赤い風邪には〇〇」といったコピーライティングが使用されるようになり、風邪にもいくつか種類があるんだなと、なんとなく認識している方も多いかと思いますが、そもそもこの「青い風邪」「赤い風邪」という言い回しは、(恐らく)風邪に対する漢方薬の処方をヒントにしたものではないかと思います。
つまり、ここまで読んでいただいた方にはもうお分かりと思いますが、「青い風邪」とは、『傷寒論』の時代の「寒さによる風邪」であり、「赤い風邪」とは、明・清時代から使われるようになった「温病学」の「熱からの風邪」ということになります。
青い風邪の特徴
- ゾクゾクと寒気がする
- 発熱
- 水のような鼻水や痰が出る
- 頭痛がする
- 関節や筋肉が痛む
「青い風邪」とは、寒さによって生じた風邪のことで、東洋医学・中医学では「風寒証」と言います。
治療方針は、温めながら発散し解熱する。
処方は葛根湯などになります。
赤い風邪の特徴
- 発熱、少々の悪寒
- 喉が赤く腫れて痛む
- 粘った痰や鼻汁が出る
- 尿の色が濃い
「赤い風邪」とは、熱を特徴にして生じた風邪のことで、東洋医学・中医学では「風熱証」と言います。
治療方針は、冷やしながら発散し解熱する。
処方は銀翹散などになります。
風邪の種類や時期によって使い分ける
以上のように、大まかに言えば、風邪には、寒さによって生じる風邪と、熱によって生じる風邪の二系統があり、そしてそれぞれに処方が異なるということになります。
さらに言えば、風邪は次から次へと変化かするように、とても動きが早いものですので、風邪の初期、中期、後期、こじらせたもの、咳がメインのものなどがあることから、さらに細かく分類して漢方薬の処方を決めた方が治りが良いものです。
このように、風邪の特徴を分類し、さらにどのステージにあるかを分析することで、漢方薬を決めていく必要があり、そうすれば、こじらせることなくピタッとうまく治めることができるものなのであります。漢方薬の助けを借りて風邪が治ると、身体は自分の体力を温存しながら風邪を追い出すことができるので、風邪の後はスッキリと気持ちの良い感覚を得ることがほとんどです。
風邪にかかったら、まず慌てる必要はありません。
そして“風邪=葛根湯”という方程式にこだわることなく、できましたら、近くの漢方薬店にご相談して、ご自身に合った漢方薬を処方してもらうことをお薦めいたします。そしてスッキリ治って、またご自身の生活に、気持ちよく戻っていただけたらと思います。
Save Your Health for Your Future
身体と心のために
自分を守り、家族を守る漢方の力
皆様とともに答えを見つけていきます
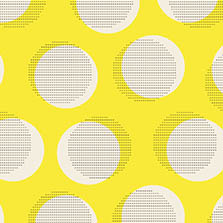
Open Your Door for Your Healthy Future
東洋医学・中医学の力を
日頃の生活に取り入れて
よりよい未来を想像していく鍼灸院

鍼灸師としてキャリアを始め、現在は東洋医学・中医学をさまざまな角度から学び、漢方薬、気功などにも精通しております。日々精進、皆様のお役に立てるように奮闘しております。

薬戸金堂・源保堂鍼灸院 院長
東洋遊人会・会長/日本中医会・会長
瀬戸郁保
鍼灸院併設の漢方薬店

薬戸金堂・源保堂鍼灸院のご案内
東京の表参道にある薬戸金堂は、主にイスクラ産業の漢方薬を取り扱う薬店です。
鍼灸院を併設しているので、より的確な処方とアドバイスをすることができます。
Contact us
東京都渋谷区神宮前4-17-3 アークアトリウム101
TEL.03-3401-8125
Find us on socials
健康で豊かな生活のためにお役に立てること
薬戸金堂・源保堂鍼灸院は皆様の健康な生活のために、東洋医学・中医学で貢献させていただきます。