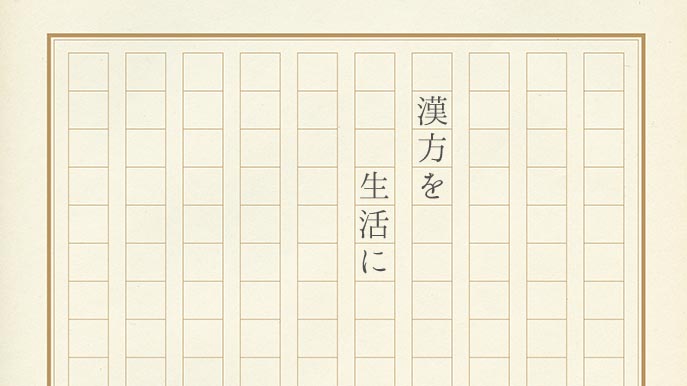【漢方薬のはなし】漢方はいつ入ってきた?
漢方薬に流派はありますか?
漢方について言うと、日本では、奈良や平安時代から少しずつ中国より伝来してきたものを使ってきました。明治に入るまでは、医薬品といえば漢方薬のことを指し、漢方薬が医療のメインだったわけです。今メインと申しましたが、何か対抗するものがあったわけではなく、そもそもそれしかなかったわけですけども、そういった漢方薬だけの歴史は日本だけでも約1300年もあったわけです。一方、漢方薬の源流である中国では、漢方薬は有史以前から今日まで利用されてきたわけですから、優に4000年の歴史があるわけです。
漢方薬は、これだけ長きに渡って私たち人類に多くの恩恵を与えてくれているのですから、当然そこにはさまざまな変遷や紆余曲折、そして発展があり、さらには、漢方薬が伝播した先の地域によって、その風土や民族に合った形で変化を遂げてきたわけです。
そう言った背景がある漢方薬ですから、流派や、師匠の筋による違いといったものが存在するわけです。これは、どの流派が正しいとか、どの流派が優れていると言ったことではなく、時代とニーズに合わせて、いかに漢方薬が柔軟に対応し、そして人類の健康維持のために寄り添ってきたかの証左ではないかと思うわけです。
江戸からの日本漢方
江戸時代は平和な時代が続いたため、庶民の学問意欲も高まり、民衆における文化芸術が爛熟した時代と言われています。この時代背景のもと、哲学もまた日本風なものが出てきたわけですが、その中の一人が伊藤仁斎(1627〜1705)という儒家で、復古学というものを唱えました。
その復古学の影響が医療にもやってきて、韓の時代の医術に帰らねばならないという動きが盛り上がりました。この気運が高まる中で現れたのが、吉益東洞(1702〜1173)です。吉益東洞は、張仲景(150?-219)の『傷寒論』を整理し、これを一つ一つ正しいことを実証していきました。吉益東洞は、一生の間にすべての処方を実証することはできなかったのですが、できた分は『類聚方』と言う書物にまとめ出版し、当時のベストセラーになりました。吉益東洞のあとは、尾台榕堂(1799-1870)がその意志を受け継いでその医術を完成しました。
吉益東洞はカリスマであったため、日本の漢方に大きな足跡を残し、今日の日本の漢方薬の処方にも大きな影響を与え続けています。
何事もそうですが、一人のカリスマが行ったことはあまりに光が強すぎて、そこには功罪あるものだと私は考えますが、大きな羅針盤となって日本漢方の系譜をブレずに支えた功績は認めざるを得ません。
Save Your Health for Your Future
身体と心のために
自分を守り、家族を守る漢方の力
皆様とともに答えを見つけていきます
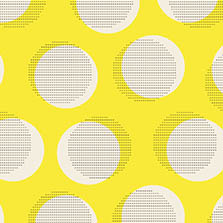
鍼灸師としてキャリアを始め、現在は東洋医学・中医学をさまざまな角度から学び、漢方薬、気功などにも精通しております。日々精進、皆様のお役に立てるように奮闘しております。

薬戸金堂・源保堂鍼灸院 院長
東洋遊人会・会長/日本中医会・会長
瀬戸郁保
鍼灸院併設の漢方薬店

薬戸金堂・源保堂鍼灸院のご案内
東京の表参道にある薬戸金堂は、主にイスクラ産業の漢方薬を取り扱う薬店です。
鍼灸院を併設しているので、より的確な処方とアドバイスをすることができます。
Contact us
東京都渋谷区神宮前4-17-3 アークアトリウム101
TEL.03-3401-8125
Find us on socials
健康で豊かな生活のためにお役に立てること
薬戸金堂・源保堂鍼灸院は皆様の健康な生活のために、東洋医学・中医学で貢献させていただきます。